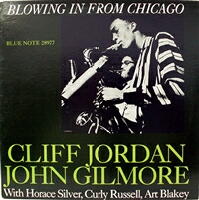ディス・イズ・クリス
ディス・イズ・クリス
(THIS IS CHRIS)
クリス・コナー(CHRIS CONNOR)の「ディス・イズ・クリス」(THIS IS CHRIS)です。
●BETHLEHEMのオリジナル盤、モノラルになります。レコード番号はBCP-20。
このレコードは、1955年に録音・リリースされたもので、全編コンボ仕立てのバッキングによりジャズ・ボーカルの楽しさを伝えてくれる好盤です。
パーソネルは、クリス・コナーのボーカル、ピアノにラルフ・シャロン、ベースにミルト・ヒントン、ドラムスにオシー・ジョンソン、ギターにジョー・ピューマ、フルートにハービー・マン(!)、トロンボーンにJ.J.ジョンソンとカイ・ウィンディングという興味深いメンバーです。
収録曲は、A面に「Blame It On My Youth」、「It’s All Right With Me」、「Someone To Watch Over Me」、「Trouble Is A Man」、「All This And Heaven Too」の5曲、B面に「The Thrill Is Gone」、「I Concentrate On You」、「All Dressed Up With A Broken Heart」、「From This Moment On」、「Ridin’ High」の5曲、計10曲です。
クリス・コナーといえば、例のケントン3人娘の一人でして、ケントンはハスキーな声がお好きだったようで、ご多分に漏れずクリスもハスキーな声で聴かせてくれます。前任者のジューン・クリスティがケントンに推薦したとかいう話しですが、真相は定かではありません。1952年にケントン・バンドに入りましたが、1年足らずの1953年には早くも独立しています。下世話ですが、おそらくはまたしてもケントンの助平根性が為せる業かと勘繰ってしまいますね。その数年後、ケントンは在団中のアン・リチャーズをものにしますから、大体はそういう根性で歌手を雇っていたのかい、と言いたくもなりますね。ケントンはエライ先生には間違いないのですが、あのニヤケタ表情にはキモイものがあります。失礼。
閑話休題。ケントンの下を辞してから録音したのが「ベツレヘム3部作」とか呼ばれている「Lullabys Of Birdland」、「ThisIs Chris」、「Chris」で、このアルバムは3部作の30cmLPとして2番目にリリースされたようですが、録音年月は最も新しい部類のものになります。最後の「Chris」は従前に録音したものの残りテイクを集めたものと理解するのが正しいようです。要するに、1953年の12月と1954年の8月と1955年の4月の3回に録音したものを30cmLPの時代になって3枚のアルバムに分けてリリースしたということになりますね。
そういえば、ジャケットなんですが、この3部作のうちでは「This Is Chris」が一番マシな出来かもしれません。いろいろ種類があるようですが最も有名な「Lullabys Of Birdland」のジャケット写真はホントにいただけません。鼻まで上を向いてアングリ大きな口を開けているショットは下品と紙一重と言えなくもありません。何故に採用されたのか、蓋し謎ですね。と言っても私は2枚も持ってますが…。「Chris」にしても、ややアートは感じるものの大きな口を開けているショットには間違いなく、あの大きな口に何か秘密でもあるんかい、と言いたくもなります。「This Is Chris」も実は口を開いているのですが、残りの2枚ほど大っぴらにあけすけではないところに好感が持てますね。
さて、ケントン3人娘で見渡しますと、アネゴ肌で少々トウのたったアニタ・オデイ、キュートなジューン・クリスティ、に比べてクリスは確かに「クール」という表現が最も当たっている存在でした。決して艶っぽいわけではなく、かと言ってカマトト風でもなく、表現が難しいのですが、冷たい「クール」ではなくて「イカシタ」意味での「クール」が相応しいように思います。
彼女は1927年生まれですから、この頃27歳です。当時で言えば適齢期を若干過ぎたもののトウがたつ前で、オバハンの貫禄ボーカルとは違う微妙なニュアンスを伝えています。この辺の微妙さが聴く方としては堪らんのでしょうね。一時期のジャズ喫茶で人気盤だったことは当然の帰結だったと言えます。
当の本人が意識的にしていたとは思えないのですが、ノリノリにまでは至らない軽妙なスイング感と知性を感じさせるようなアプローチをして、「クール」と言わしめたボーカルを披露しています。男性だけではなく、女性をも上手に惹き付けるボーカルではないでしょうか。
バックを務めるのはコンボ・スタイルのメンバーですが、中でも興味を引くのはハービー・マンのフルートと主にB面に参加しているJ&Kです。何故だかよく分かりませんが、ハービー・マンは案外ボーカルのバッキングに付き合っています。サラ・ヴォーンの有名なアルバムにも参加してとぼけたフルートを奏していましたし、このアルバムでも結果として、字義どおりのクール一辺倒に陥らないスパイス的な役割を無意識で果たしたようにも思えます。J&Kはお馴染みのダブル・トロンボーンで、ここでも技術に裏づけされた快調なソロを聴かせます。彼等は実にやっぱり上手いですね。
「クール」という言葉で括られたオカゲか、クリスには色気も何もなくて突き放したようなボーカルだというのが定説になっています。「それがまたいいんだ」と定説に反論するが如きヒネクレオヤジもいます。結局のところ、どうなんでしょうね?
「クール」という言葉から、無味乾燥とか冷たいとか色気とは無縁のイメージを抱くのは、ちょいと早計のようです。確かに滲むようなムンムンの色気があるわけではありません。ビールで例えればいわゆる辛口とされるドライ・ビールみたいなもので、コクや濃度を楽しむべきエビス型のビールではないといったところでしょうか。本来のビールで言えば、エビス型が正道ですが、最近はドライ・ビールを好む御仁が増えているそうです。ならば、ボーカルのドライ・ビール型であるクリス・コナーも人を惹き付ける魅力が横溢していることには間違いなさそうですね。「クール」という言葉に惑わされないようにしたいものでした。
まあ、色っぽいだけで、あるいはルックスや仕草だけで、歌の情感など全く無いに等しいようなインチキ「美人歌手」が流行るご時世においては、クリスの歌唱は巷間言われる色気不足を補って余りある素晴らしいものだと結んでおきましょう。
※このレコード評は、旧き佳き時代とジャズへの想いを込めた音化店主:能登一夫の評文です。