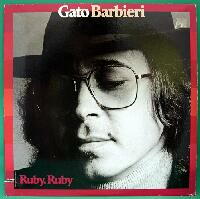ベイシー/ベネット
ベイシー/ベネット
(BASIE/BENNETT)
カウント・ベイシー、トニー・ベネット(COUNT BASIE, TONY BENNETT)の「ベイシー/ベネット」(BASIE/BENNETT)です。
●ROULETTEのオリジナル盤、モノラル仕様になります。レコード番号はR25072。
このレコードは、1958年にROULETTEからリリースされたもので、それこそアメリカを代表する歌い手であるトニー・ベネットがカウント・ベイシー楽団と共演した注目盤です。録音年には1958年と1959年の2説がありますが、レーベルに「1958」の記載がありますから1958年が正しいんだと思います。
サブ・タイトルは「ベイシーとオーケストラがスイングし、ベネットが歌う」になり、「風が吹けば桶屋が儲かる」的な韻でも踏んでるんでしょうか。そのまんまの表現ですけど、正にその通りのフレーズで笑っちゃいます。
パーソネルは、ピアノにカウント・ベイシー、ラルフ・シャロン、トランペットにスヌーキー・ヤング、サド・ジョーンズ、ウェンデル・カリー、ジョー・ニューマン、トロンボーンにアル・グレイ、ヘンリー・コーカー、ベニー・パウエル、サックス陣にマーシャル・ロイヤル、フランク・ウェス、フランク・フォスター、ビリー・ミッチェル、チャーリー・フォークス、ギターにフレディ・グリーン、ベースにエディ・ジョーンズ、ドラムスにソニー・ペイン、そしてボーカルにトニー・ベネットというメンバーです。
収録曲は、A面に「Life Is A Song」、「Plenty Of Money」、「Jeepers Creepers」、「Are You Havin’ Any Fun」、「Anything Goes」、「Strike Up The Band」の6曲、B面に「Chicago」、「I’ve Grown Accustomed To Her Face」、「Poor Little Rich Girl」、「Growing Pains」、「I Guess I’ll Have To Change My Plans」の5曲、計11曲になります。A面の1曲目は「Life Is A Song」で、のっけからの溌剌たるアンサンブルから、ややしゃがれ気味のトニーの声がイカシてます。「ライッフ・イズア・ソング」てな歌唱に寄り添うグリーンのギターが堪りませんね。
2曲目は「Plenty Of Money」でして、「底抜けにハッピーでやんす」てなノリで最後まで一気です。そりゃあ、彼女に沢山のお金がついてくりゃハッピーでやんすね。トニーの器楽風歌唱が聴かせます。ソロは多分フランク・フォスターでしょう、ちょいとフガフガなのが笑えます。
3曲目が「Jeepers Creepers」。ベイシーのポツポツ・ソロが泣かせます。数多のボーカリストが歌っていますので、殊更トニーがどうのこうのというわけにはいきませんが、元々はサッチモが歌うべき曲なんだそうで、それを幾分思い出させるような歌唱にはなってるようです。
4曲目は「Are You Havin’ Any Fun」。「お楽しみはある?」てなノリなんでしょうか? 途中の「ナッツ!」という叫びがそれもんを意識させますね。「ピーナッツ」はロッキードの件もあって、大金を想像させる隠語のようですけど、ここでの「ナッツ」は何なんでしょう。ボーカルとアンサンブルのシンクロがシンクロナイズド・スイミングに劣らず魅せてくれますよ。
5曲目は、ご存知コール・ポーターの名曲「Anything Goes」です。私はこの曲が好きでして、「エ~ニシング・ゴーズ」のフレーズはヨガレます。案外に素直な歌唱で始まったと思いきや、途中の「ダーッダ、ダディ、ダディー」がふざけてます。けど、やっぱり上手いもんでした。
6曲目が「Strike Up The Band」、ガーシュインの曲です。またもやフランク・フォスターらしきソロが挟まれて、「Hey Mr.Leader, Hey Mr.Leader, Strike Up The Band」で終わります。カッコいいとはこのことでしょうね、片面の最後に最適です。
B面の1曲目が「Chicago」、これもご存知の曲でシナトラの歌唱は一際有名ですね。ベイシーがこの曲を演じたのはあまり記憶にはありません。あまりにもミーハーすぎて嫌ってたんでしょうか?「シカゴ」と言えば、ギャングの街みたいなイメージを安易にも抱いてしまいます。そういえば「スティング」の舞台もシカゴでしたね。良かったなあ、あの映画。学生時代に中野で観たことを思い出しました。
2曲目は「I’ve Grown Accustomed To Her Face」です。「彼女の顔に慣れちゃった」てな意味ですか。まあ、美人も三日で飽きるそうですから、世の東西を問わずに同じような印象なんでしょう。でもブサ○クよりも美形の方がいいですよねっ、ノータリンでは困りますが…、失礼。
3曲目は「Poor Little Rich Girl」、そのまま訳せば「かわいそうな小さな金持ちの少女」になりますが、何のことか全然分かりません。正味、金だけあっても幸せじゃないってなもんですか? 無いよりは有った方がいいに決まっているんですけど、愛のない生活はかわいそうですから、そういうことですか。ウチには金は無いけど幸せですから、きっと優ってますね、ヘヘヘッ。ここでのバンド・パワーは底抜けにイッテます。サド・ジョーンズと思しきトランペットがブイブイ言わせてますから、お分かりですね。
4曲目が「Growing Pains」。「産みの苦しみ」みたいな意味にも取れますが、ホントにそうなんでしょうか? 産むときは皆さん苦しんで往生されるようですけど、ちょいと違う意味なんじゃないの。
最後の曲が「I Guess I’ll Have To Change My Plans」で、「計画を変えねばならんでしょう」ということで、要はアタックの仕方を変えようかみたいな意味になりますね。彼女に中々真意が伝わらないから、攻略方法を再考します的なフレーズです。ついでにベースとギターがフィーチュアされてますから、確かにちょいと演出を変えたことには間違いありません。
この当時、ベイシーは54歳、トニー・ベネットは32歳、既にベイシー・バンドはアメリカ最高のビッグバンドの一つとして名声を博しており、ニュー・ベイシーとしての活躍も大したものでしたが、トニーはこれからという年代になりますか。確かデビューが1950年ですから、後の風格はこの後に培われたものですね。母国アメリカではトニーは名士の最たるものです。
さて、実はこのアルバム中でベイシーがピアノを奏しているのは1曲目の「Life Is A Song」と3曲目の「Jeepers Creepers」の2曲で、その他のピアノ担当はラルフ・シャロン、すなわちトニー・ベネットのお抱えピアニストとでも言うべき人が奏しています。もちろん、すべてのコンダクトはベイシーです。トニーにとってはラルフ・シャロンのピアノの方が歌い易かったのかもしれませんが、ベイシーのピアノの方がスインギーなノリでは優っているようにも聴こえます。ベイシーは歌伴を好まなかったという伝説もありますけど、歌手と共演した殆どは名盤ですよね。シナトラ然り、サラ然り。
ベイシーの奏しないその他では、ソニー・ペインが叩きまくる「Strike Up The Band」やフレディ・グリーンの伴奏による「Growing Pains」なんかが聴きものです。
しかし、トニー・ベネットは相変わらず元気ですね、今年で82歳だというのに、一昨年だったかに「DUETS」とかいうCDをリリースして、未だにスーパー元気なところを聴かせています。最初に聴いたときには「歳とったなあ」というのが第一印象でしたけど、元気なのには脱帽ですね。ポール・マッカートニーでは太刀打ちできていなかったような…。決して暗くはならず、それなりのアドリブを効かせた歌唱で、根っこのしっかりした声に驚きます。
※このレコード評は、旧き佳き時代とジャズへの想いを込めた音化店主:能登一夫の評文です。
 イット・マイト・アズ・ウェル・ビー・スィング
イット・マイト・アズ・ウェル・ビー・スィング
(IT MIGHT AS WELL BE SWING)
カウント・ベイシー、フランク・シナトラ(COUNT BASIE, FRANK SINATRA)の「イット・マイト・アズ・ウェル・ビー・スィング」(IT MIGHT AS WELL BE SWING)です。
●REPRISEのオリジナル盤、ステレオ録音になります。
タイトル通り、カウント・ベイシー・オーケストラをバックにシナトラが歌ったアルバムで、主なパーソネルは、ピアノにカウント・ベイシー、ギターにフレディ・グリーン、ベースにジョージ・カトレット、ドラムスにソニー・ペイン、トランペットにハリー・エディソン、ジョージ・コーン、アル・アーロンズ、ウォーレス・ダベンポート、ドン・レイダー、アル・ポーキノ、サックスにフランク・フォスター、チャールズ・フォークス、マーシャル・ロイヤル、フランク・ウェス、エリク・ディクソン、トロンボーンにヘンリー・コーカー、グローヴァー・ミッチェル、ビル・ヒューズ、ヘンダーソン・チェンバース、ケニー・シュロイヤーとなっており、その他数名によるストリングスが引っ付いています。
このレコードは1964年に録音され、結構な強力メンバーによるベイシー楽団とシナトラとの共演盤、REPRISE第2作になります。シナトラのセルフ・レーベルだったREPRISEには3枚の共演盤があり、もう二つは「SINATRA-BASIE」と「SINATRA AT THE SANDS」です。
アレンジと指揮をクインシー・ジョーンズが担当しており、彼ならではの洒落つつ迫力のある音楽をもたらしています。いつの時代でもクインシーは中々のやり手で、楽しませてくれます。金儲けに専念しているところもありますから、一部からはバカにされていますが…。
REPRISEは、CAPITOLとの契約が終了間際になったシナトラによって1961年にパーソナルあるいはセルフ・レーベルとして設立されています。当時の所属アーティストには、娘のナンシー・シナトラ、ディーン・マーティン、サミー・デイヴィス・Jr.などがいます。1963年にはワーナー・ブラザーズ・レコードの子会社になり、1967年には親会社ごと売却されて、セブンアーツの傘下になったのですが、不思議とREPRISEのレーベルはそのまま残っています。今もロックのアルバムを中心にリリースしており、ワーナー・ブラザーズ・レコードのサブ・レーベルとして健在のようです。
閑話休題。何故にシナトラがベイシーとの共演を好んだのかは分かりませんが、相性はバッチリのようです。どちらかと言うとカンサス仕込みの田舎風スウィングが身上のベイシーと白人・おしゃれ系スウィングのシナトラとの邂逅は、結果として非常に洒落たスウィング形態を生み出したようですな。
収録曲は、A面に「Fly Me To The Moon」、「I Wish You Love」、「I Believe In You」、「More」、「I Can’t Stop Loving You」、B面に「Hello, Dolly!」、「I Wanna Be Around」、「The Best Is Yet To Come」、「The Good Life」、「Wives And Lovers」の5曲、計10曲です。それぞれ3分くらいのナンバーが続きますので、両面で30分未満という短めのレコードですが、物足りなさは感じません。あっという間に終わるものの、満足感は一入かなと思います。なんせ両者ともウマイもんねえ。
A面のトップが「Fly Me To The Moon」、B面のトップが「Hello, Dolly!」、多分に意図的なんですが、この構成は見事です。CDの連続再生では知り得ないゾクゾク感がここにはあります。
初っ端の「Fly Me To The Moon」は、正しくシナトラお誂え向きの曲。ジメジメ感は全くなく、変な情感も加えずにストレートに歌っているんですが、それこそがこの曲の真髄かもしれません。文字通り月まで吹っ飛んで行きそうです。
片やB面トップの「Hello, Dolly!」はお馴染みのミュージカル・ナンバーで、サッチモによる名唱が有名ですが、ここでシナトラは殊更ハッピーに歌っており、ちょいとサッチモを意識したようなフレーズも交えています。元々明るい曲ですから、こういう解釈が妥当なのかもしれません。
ところで、ジャケット表面にはシナトラとベイシーの、ちょいとピンボケで切り抜きミエミエの顔写真が載っていますが、シナトラの下にある「FRANK」は分かるとしても、ベイシーの下に書かれている「SPLANK」は何なんでしょうね? 一応英和辞典や英辞郎なんかも調べてみましたが、こんな単語は出てきません。「SPLANG」なら「辛辣な言葉」という意味で、「PLANK」ならアホ、バカ、マヌケみたいな意味なんですが…。一体ナニを意味しているのか、ご存知の方がいらっしゃったら是非教えてください。
※このレコード評は、旧き佳き時代とジャズへの想いを込めた音化店主:能登一夫の評文です。
 ベイシー&ズート
ベイシー&ズート
(BASIE & ZOOT)
カウント・ベイシー(COUNT BASIE)とズート・シムズ(ZOOT SIMS)による「ベイシー&ズート」(BASIE & ZOOT)です。
●PABLO原盤のRCAによるリイシュー盤かと思われます。
1975年当時にPABLOがどういう状況にあったのか知る術がありませんので、一応リイシュー盤としておきます。ただ、録音場所のクレジットがニューヨークのRCAスタジオですので、もしかしたらオリジナルかもしれません。申し訳ございませんが私にはよく分かりません。
パーソネルは、ピアノとオルガンにカウント・ベイシー、テナー・サックスにズート・シムズ、ベースにジョン・ハード、ドラムスにルイ・ベルソンという、正にベテラン名手達の演奏です。
このレコードは1975年に録音されたもので、プロデューサーのノーマン・グランツはその交際範囲の広さを武器に、いわゆるビッグ・ネームを交配して次々にアルバムをリリースしていました。このレコードもそういう1枚ではありますが、放っておけばどこまで行くか分からないズートをベイシーが上手く牽制しつつ盛り上げているようで、上手くまとまった盤かと思います。
最後の収録曲(「I Surrender, Dear」)で、ベイシーはオルガンを弾いています。これがまた何ともそれらしい趣きで、ジャズ・クラブにでも居るような雰囲気です。古きジャズを彷彿とさせる演奏ですが、オルガンの響きとズートのテナーとの絡み合いが堪りません。
他では、キング・コールで有名な「It’s Only A Paper Moon」でのベイシーの軽快なピアノや、ベイシーとズートが共作した「Blues For Nat Cole」(そのナット・キング・コールに捧げた曲です)なんかが聴きものです。このレコードには両者の共作が3曲収録されていますが、その出来はどれもゆったりとして暖かいものを感じさせてくれます。
いずれにせよ、メンバーにはまだまだ余裕が感じられ、それ故にいろんな表情を見せてくれる好盤かと思います。ジャケット写真の意味するところを今一つ掴みかねるところですが、結構スモーカーだったんですな、ズートは…。
※このレコード評は、旧き佳き時代とジャズへの想いを込めた音化店主:能登一夫の評文です。
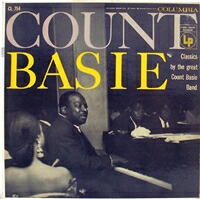 カウント・ベイシー・クラシックス
カウント・ベイシー・クラシックス
(COOUNT BASIE CLASSICS)
カウント・ベイシー(COUNT BASIE)の「カウント・ベイシー・クラシックス」(COOUNT BASIE CLASSICS)です。
●COLUMBIAのオリジナル盤、モノラルになります。レコード番号はCL-754。
このレコードは、1955年にCOLUMBIAからリリースされたものですが、それ以前の録音を集めて構成されており一種のオムニバスにあたります。とはいえ、演奏の優秀さからCOLUMBIAのオリジナル盤と見做しても問題はないかなと思います。1940年の3月から1946年の2月までの間で録音されたものを集めてあります。
パーソネルは、録音年月が多岐に渡っていますので、それぞれの曲で異なるパーソネルと言えなくもありません。主だったところだけ挙げておけば、ピアノにカウント・ベイシー、トランペットにハリー・エディソン、ジョー・ニューマン、バック・クレイトン、アル・キリアン、エド・ルイス、エメット・ベリー、トロンボーンにディッキー・ウェルズ、テッド・ドネリー、エリ・ロビンソン、ルイ・テイラー、ロバート・スコット、ジョージ・マシューズ、ジェームズ・ジョンソン、ダン・ミラー、ヴィック・ディッケンソンなど、サックスにジェームズ・パウエル、ルディ・ラザフォード、バディ・テイト、アール・ウォーレン、エリ・ロビンソン、ジャック・ワシントン、ドン・バイアス、イリノイ・ジャケー、レスター・ヤングなど、ギターにフレディ・グリーン、ベースにロドニー・リチャードソン、ウォルター・ペイジ、ドラムスにシャドウ・ウィルソン、ジョー・ジョーンズ、ボーカルにジミー・ラッシング、というようなメンバーです。
収録曲は、A面に「Red Bank Boogie」、「It’s Sand, Man!」、「Jimmy’s Blues」、「The Mad Boogie」、「Goin’ To Chicago Blues」、「Avenue C」の6曲、B面に「The King」、「Taps Miller」、「Rusty Dusty Blues」、「Rambo」、「You Can’t Run Around」、「One O’clock Jump」の6曲、計12曲になります。
A面の1曲目は「Red Bank Boogie」で、ブルースではなくてブギーですね。冒頭から元気バリバリ・ウキウキの演奏です。40年代といえば、ベイシーも若かったんですね、40代ですよ。ベイシーのピアノに呼応するようにサックスなどのアンサンブルが粋に迫ります。大体ベイシーの故郷がレッド・バンクですから、彼にして思いの募る曲なんでしょう。翻訳ソフトによりますと「赤い銀行は浮かれます」だそうで…何のこっちゃ。
2曲目は「It’s Sand, Man!」でして、何やら意味不明なタイトルではあります。サンドイッチ・マンとは違うようですね。これはサンド(砂)です、ってなもんですけど? 砂場遊びは幼稚園くらいの頃によくやりましたね。大体がトンネルを作ったり掘ることが多かったんですけど、たまに何やら軟らかい固まりみたいな砂が出てきて、結局それは猫あたりのウンチだったんでしょうね、当時は知る由もありませんでしたけれど…。これまたベイシーやグリーンとアンサンブルの対比が見事で、浮かれちゃいますよ~。
3曲目が「Jimmy’s Blues」。ジミー・ラッシングの歌が入っています。まあ、タイトルからして彼が歌っているだろうことは容易に想像つきまして、正にその通りの名演でした。中年のオッサン歌唱ですけど、レトロな雰囲気あるのが彼の魅力ではあります。あのゴツそうな顔付きからは想像できない中高域の張りで、案外に優しいオッサンだったんでしょうか。
4曲目は「The Mad Boogie」。マッドなブギにしてはベイシーのソロが結構目立っていて、別に殊更マッドではないですね。しかしマッド人が浮かれるだけでなくて常人も浮かれますから、ベイシーの胆は如何ほどかと嬉しい曲です。ベイシーとグリーンが鮮明に聴こえて、相変わらずやってます。
5曲目は「Goin’ To Chicago Blues」で、またもやジミー・ラッシングがしみじみと歌います。でもシカゴのブルースですから、それもんです。シカゴへ行ってからのブルースだそうですから、シカゴに着いたらギャングとブルースだらけで驚いたみたいなノリでしょうか? シカゴでブルースといえば、ついつい憂歌団の「シカゴ・バウンド」と比べてしまいますが、だいぶ違いますね。冒頭のトランペットは誰か不明です。
6曲目が「Avenue C」。もう元気がいいんだから、ベイシー・バンドさん。サックスとトランペットのソロは私では判別不能ですが、バリバリのうちに終わってしまいます。「C通り」ってカウントのCかシカゴのCなのか、悩みますね。案外フツーに「中央通り」だったりして、興味は尽きません。作者がバック・クレイトンなので、自分のCでしょうかね。真相は不明です。
B面の1曲目が「The King」、王様ですね。一体ナニの王様かは知りませんが、相変わらずの元気一杯プレイです。ベイシーやグリーンらとの対比はこの頃の方が明快なようで、割り切りが明解で楽しめます? 途中のサックスソロが誰かはまたまた不明ですけど、一応イリノイ・ジャケーにでもしておきましょうか…。
2曲目は「Taps Miller」です。「タップの粉屋」とも訳せそうですけど、これは「ミラーのタップ」かもしれません。「Tap」じゃなくて「Taps」ですから、そうなると「消灯ラッパ」という意味もあるようです。いずれにしてもよく分かりませんが。少々ホンワカしたテーマの後に続くソロたちは活気ムンムンで、ホーンの輝きを前面に打ち出しています。消灯ラッパだとすれば威勢がよすぎますが、このくらいでないと受けなかったんでしょう。
3曲目は「Rusty Dusty Blues」です。錆びた埃っぽいブルースでして、ジミー・ラッシングが歌います。レトロ気分が横溢した、古い映画でも見ているような気分にさせてくれます。聴きようによっては古の演歌みたいに聴こえなくもありません。
4曲目が「Rambo」で、そのまんま「ランボー」ですが、かのスタローンの映画とは違うようです。単純に乱暴なアレンジではなくて、中々に計算された粋なアレンジでした。それぞれのソロは短いものの丹精込めて端整にまとめています。ザッツ・エンターテインメントとはこのことですね。
5曲目は「You Can’t Run Around」、ここでもジミー・ラッシングの声が聴けます。日本では彼のラスト・レコーディングのみ有名ですが、若かりし頃の歌声も一聴の価値は十分にありますね。確かにこのテンポでは走り回ることはできません。
最後の曲が「One O’clock Jump」で、お馴染みのベイシー・テーマ曲です。この当時のは晩年のショート・ヴァージョン・テーマでなくて割りと長めに聴けますから、通には嬉しい選曲ですね。
※このレコード評は、旧き佳き時代とジャズへの想いを込めた音化店主:能登一夫の評文です。
 ダンス・アロング・ウィズ・ベイシー
ダンス・アロング・ウィズ・ベイシー
(DANCE ALONG WITH BASIE)
カウント・ベイシー(COUNT BASIE)の「ダンス・アロング・ウィズ・ベイシー」(DANCE ALONG WITH BASIE)です。
●ROULETTEのオリジナル盤、モノラル録音になります。
カウント・ベイシーには「シング・アロング・ウィズ・ベイシー」というLH&Rと組んだ有名盤があり、このレコードはそれを意識して作られたものかと思います。「歌う」のが「踊る」に変わったわけですが、別にこれを聴いて踊らにゃならん、というものではなく、快調な演奏をお楽しみいただけるかと思います。
主なパーソネルは、ピアノにカウント・ベイシー、ギターにフレディ・グリーン、ベースにエディ・ジョーンズ、ドラムスにソニー・ペイン、トランペットにサド・ジョーンズ、ジョー・ニューマン、スヌーキー・ヤング等、サックスにフランク・フォスター、マーシャル・ロイヤル、フランク・ウェス等、トロンボーンにヘンリー・コーカー等となっています。
このレコードは1959年に録音された、50年代後半におけるベイシー楽団の強力メンバーによる演奏で、極上のビッグ・バンド・サウンドを堪能できます。
※このレコード評は、旧き佳き時代とジャズへの想いを込めた音化店主:能登一夫の評文です。
 ディス・タイム・バイ・ベイシー!
ディス・タイム・バイ・ベイシー!
(THIS TIME BY BASIE!)
カウント・ベイシー(COUNT BASIE)の「ディス・タイム・バイ・ベイシー!」(THIS TIME BY BASIE!)です。
●REPRISEのオリジナル盤、モノラル録音になります。
主なパーソネルは、ピアノにカウント・ベイシー、ギターにフレディ・グリーン、ベースにバディ・カトレット、ドラムスにソニー・ペイン、トランペットにソニー・コーン、サド・ジョーンズ等、サックスにフランク・フォスター、エリック・ディクソン、マーシャル・ロイヤル、フランク・ウェス等、トロンボーンにヘンリー・コーカー、ベニー・パウエル等となっています。
このレコードは1963年に録音されたもので、いわゆるポピュラーな楽曲をビッグ・バンド用にアレンジし、大変立派なジャズへと昇華させた好例です。アレンジは今も華々しく活躍を続けるクインシー・ジョーンズが担当しています。
「I Can’t Stop Loving You」や「Walk,Don’t Run」など、単純明快な中にもスインギーなジャズを堪能でき、ベイシーを知らない方にも好適なレコードでしょう。強力メンバーによるアンサンブルの妙を楽しむにももってこいかと思います。
※このレコード評は、旧き佳き時代とジャズへの想いを込めた音化店主:能登一夫の評文です。
 プライム・タイム
プライム・タイム
(PRIME TIME)
カウント・ベイシー(COUNT BASIE)の「プライム・タイム」(PRIME TIME)です。
●PABLOのオリジナル盤のようにも思えますが、RCAの表記がありますからリイシューかもしれません。レコード番号は2310-797で、オリジナルの番号を踏襲しているようです。
このレコードは1977年にLAで録音されたもので、かなりの好調を維持していた頃のベイシー・ミュージックを楽しめる1枚です。
カウント・ベイシー・オーケストラは1978年に来日しており、そのときのライブ盤も日本企画でPABLOからリリースされていますが、それとパーソネルは大体同じで来日時の熱気を髣髴とさせる演奏です。
パーソネルは、ピアノに御大のベイシー、トランペットにソニー・コーン、ピート・ミンガーほか、トロンボーンにアル・グレイ、カーティス・フラー、ビル・ヒューズほか、サックスにジミー・フォレスト、エリック・ディクソン、ダニー・ターナーほか、ベースにジョン・デューク、ギターにフレディ・グリーン、ドラムスにブッチ・マイルスといったメンバーで、カーティス・フラーとジミー・フォレストの参加が珍しいところです。来日時には、デニス・ウィルソンとケニー・ヒングが彼らに代わって参加していました。
録音は少々ベースが強調された感じですが、いわゆるHI-FI録音には違いなく、レンジの広そうな質感を感じさせてくれます。
アレンジの担当がサム・ネスティコですので、ダイナミックで躍動的なベイシー・サウンドを堪能でき、ある意味では大変好ましいまとまりかと思います。
1977年にこのアルバムをリリースし、1978年に来日し、1979年にはモントルーにおけるライブ盤が一世を風靡したベイシー・オーケストラです。したがって70年代後半におけるベイシーの足跡を辿るには、メンバー交代のあった77年におけるこのアルバムは欠くことのできないものかもしれません
※このレコード評は、旧き佳き時代とジャズへの想いを込めた音化店主:能登一夫の評文です。
 ベイシー・プレイズ・ヘフティ
ベイシー・プレイズ・ヘフティ
(BASIE PLAYS HEFTI)
カウント・ベイシー(COUNT BASIE)の「ベイシー・プレイズ・ヘフティ」(BASIE PLAYS HEFTI)です。
●ROULETTEのオリジナル盤、モノラル仕様です。レコード番号は、R-52011。
このレコードは1958年にニューヨークで録音され、ROULETTEからリリースされたもので、何といってもニール・ヘフティのアレンジが冴え渡る名盤ではないでしょうか。時代的にはモードが持て囃されつつあり、フリーが登場した頃ですが、オールド・ベイシー・バンドをかくもモダンに成形し直したのは、ひとえにニール・ヘフティのお陰でしょう。
このアルバムの直前に、有名な「アトミック・ベイシー」がリリースされています。結構な有名曲で彩った「アトミック」に対して、本アルバムは全曲がニール・ヘフティの作曲と編曲で占められており、こっちの方がアレンジの意図を直截的に体験できますね。どちらも名盤に違いありません。
パーソネルは、ピアノにカウント・ベイシー、トランペットにスヌーキー・ヤング、サッド・ジョーンズ、ウェンデル・カリー、ジョー・ニューマン、トロンボーンにアル・グレイ、ヘンリー・コーカー、ベニー・パウエル、テナーサックスにフランク・フォスター、ビリー・ミッチェル、アルトサックスにフランク・ウェス、マーシャル・ロイヤル、バリトンサックスにチャーリー・フォークス、ギターにフレディ・グリーン、ベースにエディ・ジョーンズ、ドラムスにソニー・ペインといった面々です。
収録曲は、A面に「Has Anyone Here Seen Basie」、「Cute」、「Pensive Miss」、「Sloo-Foot」、「It’s Awf’ly Nice To Be With You」の5曲、B面に「Scoot」、「A Little Tempo, Please」、「Late Date」、「Count Down」、「Bag-A’ Bones」、「Pony Tail」の6曲、計11曲です。
A面の1曲目「Has Anyone Here Seen Basie」から普通じゃない入り方です。高音のユニゾンで、ちょっと引いてしまいますが、活気があってよろしいね。「誰でもベイシーに会いました?」ってな訳ですけど、アルバムを聴いてるんだから、大体はベイシーに会ってるんじゃないのかと、ツッコミたくもなります。ホントに会ったわけじゃないですけど、ベイシーが亡くなられる間際の日本公演には行きましたがな、私。でも、こういうアレンジは後年まで続きますから、ヘフティ恐るべしですかね。
2曲目は「Cute」です。キュートと言われると、ついついJCやJKを想像してしまいますね? セーラー服はキュートですよね、誰が見ても。最近はブレザーとかネクタイが増えて、セーラー服のお嬢さんは減っているのが残念です。あのね、ブルセラ・マニアじゃございませんので、誤解のなきよう…。フランク・ウェスのフルートが、ああ、ヨガラセます。ソニー・ペインはブラシを使ってまっせ、粋ですねえ。キュートゆえにスティックではキツいんでしょうか。
3曲目が「Pensive Miss」、翻訳ソフトですと「考え込んでいる失敗」です。失敗して考え込んでいる方が普通なんですが、考え込んでから失敗したようで、ちょいと鬱っぽい曲でした。失敗して陽気だったら、ほとんどアホですからね(ホントは失敗じゃなくて、哀愁のお嬢さんだと思いますけど…)。最後の方で一瞬けたたましくなりますが、ベイシーゆえのご愛嬌ですか…。ただ、この曲はこのアルバムの白眉かも。アトミックでの「リル・ダーリン」に優るとも劣らぬ名曲・名演のような気もしないではないという、優柔不断な意見を述べておきます。スヌーキー・ヤングのトランペットが泣かせますよ、浸るのもまた善し?
4曲目は「Sloo Foot」、曲名は何のことかよく分かりませんが、いい感じのテンポで進みます。ユニゾンとグリーンのギターが上手い対比で、アレンジがくすぐります。フレディ・グリーンのリズムが上手く聴こえれば、大体は好ましいオーディオ・システムじゃないでしょうかね。途中のペットはジョー・ニューマンでした。
5曲目は「It’s Awf’ly Nice To Be With You」です。「あなたといられてとっても嬉しいわ」みたいな意味でしょうね。嬉しい割りにはユックリめの演奏で、マーシャル・ロイヤルのサックスがムード盛々で、ユニゾンは結構強烈で、一体ナニが嬉しいのか悩むところです。恋愛中なら、あなたといれて(いられて)嬉しいのは世の常ですから、要らぬ詮索は止めましょう。劇的な変化が思わせぶりってか?
B面に移って1曲目が「Scoot」です。「走り出せ」ってな意味でしょうが、曲調は軍隊モドキではなくて何だかアニメでも観ているような、陽気でリラックスした演奏でした。ScootしてるのがScooterですね、私もスクーターに乗ってます。ミュート・トランペットとフランク・ウェスのフルートが絶妙のコンビを聴かせてくれます。
2曲目が「A Little Tempo, Please」、「少しのテンポ、お願い」では意味不明ですね。もうちょっとやってよ、てな具合ですか? それにしてもトロンボーンがヨガリ過ぎで、アル・グレイだそうです。
3曲目は「Late Date」で、翻訳ソフトでは「遅い日付」ですけど、実際は「遅めのデート」なんじゃないのか。何だか夕暮れ時を連想させてシットリですぜ、旦那。ここでもフランク・ウェスのフルートが、うーん、スウィート! 強烈なパンチはないけれど、こんなのが乙女心には快感なんでしょうね、これしかないようなテンポで進みます。
4曲目は「Count Down」です。「秒読みしてちょ」ですけど、ホンマに秒読みしてまっせ、10から0まで。テナーはビリー・ミッチェルとフランク・フォスターの掛け合いだそうで、ベイシー・スイングここにありっ!
5曲目が「Bag-A’ Bones」、何のことかさっぱり分からない曲名です。俗語では「bag」は「女性自身」で、「bone」は「男性自身」の意味もありますけど、良からぬことを連想しそうでイケナイ曲名ですね。またもやアル・グレイのトロンボーンがフェチしてます、ユニゾンとの絡みが何ともはや…。
最後の曲が「Pony Tail」です。ヘフティはポニーテールが好きなんでしょうか? ナニを隠そう私もポニーテールはメッチャ好きです。かつてのロックンロールもしくはロカビリーな時代、ポニーテールのお嬢さんがサーキュラーなフレア・スカートを穿いて踊っておられるのはソソリますね。気が付いたときには、そういう時代は過ぎ去っていたのが残念です。まあ、そういう時代風なカフェとかクラブに行けば、今でもオールディーズな気分は楽しめて、ポニーテールのお嬢さんも居られるようですけど…。録音されたのが丁度その頃でしたから、中々に時代を読む目・耳があったということなんでしょう。
全体的に、ヘフティの作曲とアレンジが微妙に秀逸で、持っていて損のない好盤です。まだまだメジャーにはなっていなかったフルートのソロを適宜に採り上げて、立派なソロ楽器まで育てた功労者かもしれませんね、ヘフティは。フランク・ウェスがこのアルバムではやけに目立ってますよ、良かったね。
ところで、ジャケットの写真は「アトミック・ベイシー」の原爆写真とはうって変わったヒョウキン写真です。どこのチームかよく分からない野球のユニフォームを着て、ベイシーは三波春夫のごとく、あさっての方を見てニチャっと笑っています。何ともあんまり気持ちよくはないショットですね。右側で口を大きく開けているのがニール・ヘフティだそうです。ヘフティの被っている帽子は野球帽というよりは、小学校の運動会でよく見かける赤帽みたいで、笑かします
※このレコード評は、旧き佳き時代とジャズへの想いを込めた音化店主:能登一夫の評文です。
 シング・アロング・ウィズ・ベイシー
シング・アロング・ウィズ・ベイシー
(SING ALONG WITH BASIE)
カウント・ベイシー(COUNT BASIE)とランバート・ヘンドリックス・アンド・ロス(LH&R)の「シング・アロング・ウィズ・ベイシー」(SING ALONG WITH BASIE)です。
●ROULETTEのオリジナル盤、ステレオ仕様になります。レコード番号はSR-52018。
このレコードは1958年に録音されたもので、ランバート・ヘンドリックス・アンド・ロスとの共演盤になります。LH&Rは、この前作である「SING A SONG OF BASIE」で、ベイシー楽団のソロ演奏に歌詞を付けて、楽器と同じようにボーカリーズするという信じられない快挙を成し遂げているのですが、それを聴いたベイシーが「何で俺が入っていないんだ」と言ったかどうかは定かではないものの、一緒にやる羽目になった企画盤とも異色盤とも言える逸品です。
パーソネルは、ランバート・ヘンドリックス・アンド・ロス(すなわち、デイブ・ランバート、ジョン・ヘンドリックス、アニー・ロス)とジョー・ウィリアムズのボーカルをベイシー楽団がバッキングするという豪華なメンバーです。LH&Rはワールド・パシフィックと契約していたみたいですね。
収録曲は、A面に「Junmpin’ At The Woodside」、「Going To Chicago Blues」、「Tickle Toe」、「Let Me See」、「Every Tub」の5曲、B面に「Shorty George」、「Rusty Dusty Blues」、「The King」、「Swingin’ The Blues」、「Lil’ Darlin’」の5曲、計10曲です。
曲目はすべてベイシー・ナンバーで、「Going To Chicago Blues」、「Every Tub」、「Rusty Dusty Blues」の3曲にジョー・ウィリアムズが参加しています。
まず、冒頭の「Jumpin’ At The Woodside」で度肝を抜かれます。ラップのあんちゃんもビックリの急速調で、「ちゃんと発音してるんかい?」と言いたくもなりますが、してるんですね、これが。特にジョン・ヘンドリックスの早口言葉には脱帽です。いや、凄い。曲の途中からアニー・ロスのボーカルになりますが、「That’s It – That’s It – That’s It」と叫ぶ彼女の声が極めて印象的です。
その他の曲も、テンポはそれぞれ違えど見事なボーカリーズで嬉しくなります。強いて言えば、「Jumpin’ At The Woodside」、「Tickle Toe」、「Every Tub」、「Swingin’ The Blues」あたりが聴きものでしょうか。
実は、私が始めて聴いたベイシーのアルバムはこれでした。「I Gotta Go – I Wanna’ Blow」と繰り返される冒頭の曲にノックアウトされ、その後はLH&Rとベイシーのアルバムをそれとなく漁ることになりました。そのうちに、LH&Rは何だかアホらしくなってきたのですが、ベイシーは生涯の友になったのでした。
と言って、LH&Rがつまらないわけではありませんので、誤解のなきよう。特にこのアルバムなんぞは、快適なスイングが何であるか明解に答えてくれる名盤だと思います。ナニを隠そう私はこのLPを3枚ほど持っていたのでした。
ジャズを聴き出した頃は、どちらかというと田舎くさいベイシーよりも都会的なセンスに溢れたエリントンをヨガッテいたものでしたが、このアルバムに出会ってから以降はベイシーのスイング感に惹きつけられたものです。一関の○原さんじゃないですが、ベイシーは止められまへん。
大体アドリブをも含めてボーカリーズしてますから楽譜があるようなものなんですが、そう感じさせないのがスゴイんでしょう。後年にはマンハッタン・トランスファーが似たようなことをしますが、スイング感には違いがあって、ノリノリの好演はこのLPに軍配が上がりそうです。ところで、そのマントラにいくつか歌詞を提供していたのが件のジョン・ヘンドリックスでして、おとっつぁんは大したものであります。
※このレコード評は、旧き佳き時代とジャズへの想いを込めた音化店主:能登一夫の評文です。